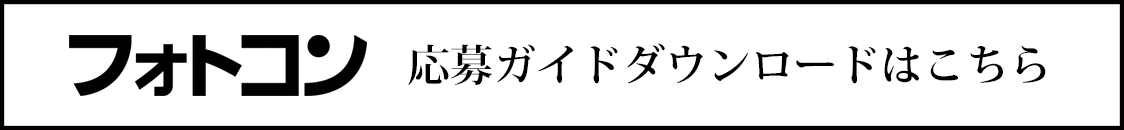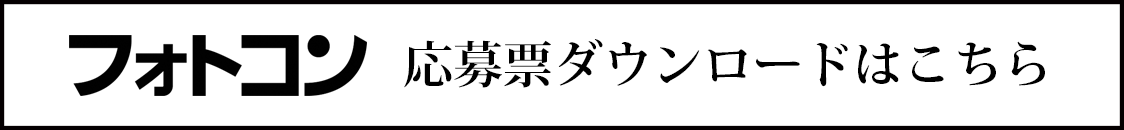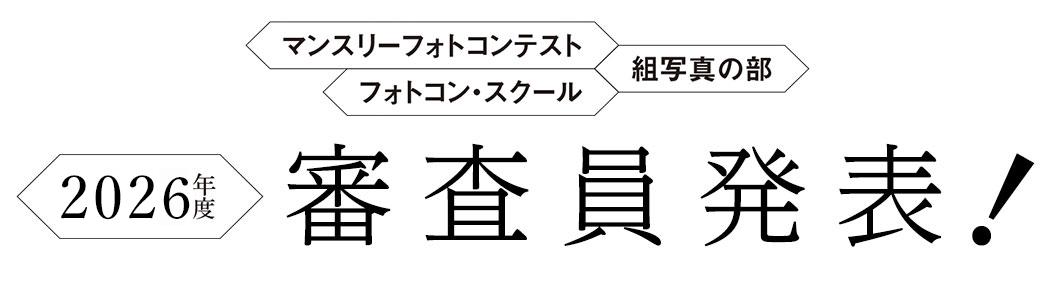
10月10日で締め切られる分からは、新年度の月例コンテストがスタートです。中・上級コース、初級コース、組写真の部、モノクロ作品招待席と部門も多数ありますので、ご自分のスタイルに合ったところへご応募ください。みなさんの作品が毎月のフォトコン誌面を作ります。最高の作品をお待ちしています!
マンスリーフォトコンテスト 中・上級コース ネイチャーフォトの部

並木 隆 (5年ぶり3回目)
1・4・7・10月号審査
何をどう感じたのかを大切にしてほしい
写真に答えはないと言いますが、それは同じ被写体でも撮影者がどう感じてどう表現したいかによって撮り方が変わってくるからです。こういうときにどうすべきかばかりを求めていくと決まった撮り方しか当てはめることができないため、どんなに素晴らしい被写体でもどこかで見たことがあるような平凡な写真になってしまいます。この被写体をどう撮ったらいいかではなく、この被写体を見て何をどう感じたのかを考えてみましょう。キレイだなだけではなく、光なのか、色なのか、形なのか、状況なのか、人それぞれ感じるところが違って当然ですし、それが個性となるのです。みなさんの個性が存分に出ている作品をお待ちしております。
なみき・たかし
1971年生まれ。高校生時代、写真家・丸林正則氏と出会い、写真の指導を受ける。東京写真専門学校(現・ビジュアルアーツ)中退後、フリーランスに。花や自然をモチーフに作品発表。著書に『一番人気のある写真教室テキストブック』(小社刊)。

菊池哲男 (7年ぶり3回目)
2・5・8・11月号審査
どんなボールが投げられてくるか楽しみ
本誌の審査は2011 年の初級コース、2019 年の中・上級コースに続いて7 年ぶり3回目、マンスリーフォトコンテスト中・上級コースとしては2回目となります。個人的にはこの間、2020年『鹿島槍・五竜岳』、2024年『四季白馬』と2冊の写真集を上梓し、大規模な写真展も開催しました。フォトコンテストは応募者がいないと成立しないわけで、年間を通してのマンスリーフォトコンテストは応募者と選者である私とのキャッチボールだと思っています。まずはどんなボールが投げられてくるのか、今から楽しみにしています。そし て応募されない読者の方にもぜひ楽しく観戦していただければと思っています。
きくち・てつお
山岳写真家。『山の星月夜』、『四季白馬』(共に山と溪谷社)などの写真集を始め、様々な媒体に作品を発表。東京都写真美術館をはじめ、各地で大規模な写真展を開催。長野県白馬村和田野の森に菊池哲男山岳フォトアートギャラリーがある。

秦 達夫 (8年ぶり3回目)
3・6・9・12月号審査
厳しく険しい道の先に“楽しさ”がある
「写真は人生を豊かにする」—フォトコンはその一端を担っていると思います。だからこそ選者は、応募者の人生に少なからず影響を与える存在であり、大きな責任を背負っているのです。実際、この場からプロの道へと進んだ方も少なくありません。そして、活躍している方々は何より写真を楽しんでいます。その” 楽しむ心”こそが評価につながるのだと思います。人生は楽しんだもの勝ち。写真も楽しんだもん勝ち。そんな思いで一年間、真剣に、そして楽しく取り組んでいきたいと思います。最後に、「楽しむこと」と「楽をすること」は違います。厳しく険しい道の先にこそ、本当の” 楽しさ”があると信じています。
はた・たつお
長野県飯田市遠山郷出身。自動車販売会社・バイクショップに勤務。後に家業を継ぐために写真の勉強を始め、自分に可能性を感じ写真家を志す。写真家竹内敏信氏の助手を経て独立。写真集に『風光の峰 雲上の渓』『秋田白神 山は恵むよ』(小社刊)ほか多数。
マンスリーフォトコンテスト 中・上級コース 自由作品の部

榎並悦子 (4年ぶり3回目)
1・4・7・10月号審査
新しい感性や表現に出会いたい
2026年の月例選者を務めさせていただきます。自由部門は本当に幅広いジャンルの応募がありますから、個性豊かな作品に出合えることがとても楽しみでワクワクしています。私が選ぶ際に大切にしたい視点は、作者が何に感動し、それをどのようにとらえ、写真に昇華させたかという点です。光や影、構図、など技術的なことも大切ですが、それ以上に被写体への深い観察力や、想いが伝わってくる作品に惹かれます。皆さの一枚一枚から、感動の核心が伝わることを楽しみにしています。新しい感性や表現に出会えることを心から期待しています。たくさんのご応募お待ちしています。
えなみ・えつこ
「一期一会」の出会いを大切に人物や自然、風習、社会問題など、幅広いフィールドで撮影を続けている主な作品に『日本一の長寿郷』『Little People』『越中八尾おわら風の盆』など。全日本写真連盟副会長(公社)日本写真家協会正会員。

清水哲朗 (6年ぶり2回目)
2・5・8・11月号審査
共感の有無が結果を左右することもある
月刊のカメラ誌が減り、本誌月例は今や貴重な場。結果に一喜一憂したり、他人の作品や選者の講評にアイデアや刺激をもらったり嫉妬したりしながら創作意欲につなげるのはとても良いことです。毎月応募する人は撮影、セレクト、プリント、発送と息つく暇もないと思いますが、吉報に報われることもあるでしょう。技術的には満点でも上位に選ばれるとは限らないのがコンテストの天邪鬼。共感の有無が結果を左右することも多々あります。本誌審査は2019-2020年の組写真の部以来ですが、自身が同じ現場に立った場合「それ以上のイメージで撮れるか」を一つの選考基準にしています。他にもありますが、それはまた今後。たくさんのご応募お待ちしています。
しみず・てつろう
1975年生まれ。モンゴルをはじめ、独自の視点で自然風景からスナップ、ドキュメンタリーまで幅広く撮影。個展開催、受賞歴多数。主な写真集は『CHANGE』『New Type』『トウキョウカラス』。(公社)日本写真家協会理事。

山﨑友也 (5年ぶり3回目)
3・6・9・12月号審査
心で感じたことをストレートに表現してほしい
おりゃぁ~っ! ワシが天才鉄道写真家の山﨑友也じゃけぇ。中・上級コース自由作品の部の審査員をやることになったけぇ、これから一年間よろしゅう頼むのぉ。というわけで、皆さん改めましてこんにちは。2026年度は中・上級コースということで、かなりハイレベルなコンテストになるのではと、今からとても楽しみにしています。ボクが皆さんに求めるのは、ずばり” 個性”です。単純にきれいな写真やどこかで見たこ とがある写真ではなく、皆さんが心で感じたことをそのままストレートに表現する、そんな作品を期待しています。ボクには想像もつかない、皆さんの感性だからこそ撮れた作品をぜひとも奮って送ってきてください!
やまざき・ゆうや
1970年広島生まれ。鉄道写真の専門家集団「レイルマンフォトオフィス」代表。独自の視点から鉄道写真を多彩に表現し、出版や広告など幅広い分野で活動中。写真集に『Memories 車両のない鐵道写真』(小社刊)など多数。
フォトコン・スクール 初級コース 自由の部

今井しのぶ (初審査)
撮影が楽しくなるメッセージを届けたい
普段はベビー・キッズフォト専門家として活動していますが、プライベートではいろんなジャンルの撮影をしていて写真を見るのが大好きです。毎月みなさんの写真を拝見できること、とてもワクワクしています。写真には撮ったときの想いが込められていて、見ている人をその瞬間に立ち会っているような気持ちにさせてくれる魅力があります。審査では作品の良さを大切にしながら、これからの撮影がさらに楽しくなるようなメッセージをお届けできればと思っています。審査にあたっては、これからの作品づくりに少しでも役立つ視点やヒントをお届けしたいです。皆さまの作品と向き合いながら、心が動く瞬間を一緒に感じられることを楽しみにしています。
いまい・しのぶ
ベビー・キッズフォト専門家。三重県出身、神奈川県川崎市にてフォトスタジオ「こどもとかめら」を運営。ファミリー撮影や初心者向けフォトレッスン、プロ養成講座を開講。書籍『こどもを撮るマニュアル本』(小社刊)ほか多数。
フォトコン・スクール 初級コース ネイチャーの部

井上嘉代子 (初審査)
見つけた時の感動を伝えてください!
2026年度のフォトコン・スクール初級コース「ネイチャーの部」を審査担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。光や色を見つけ変化を感じ、生き物や草花との出会いなど、自然に一歩足を踏み入れると魅力的な被写体があふれています。広大な風景から足元の小さな被写体まで「見つけた時の感動を表現する」それがネイチャー写真の楽しみです。私は普段、音を聞き、風を受け、においを嗅ぎ、「気づき」を大切にしています。その気づきを誰かに伝えたいと思った時がシャッターをきるチャンスだからです。皆さんの上達につながるよう、丁寧に審査していきたいと思います。伝えたい作品を楽しみにお待ちしております。
いのうえ・かよこ
1967年、岐阜市生まれ。インテリア・デザイン業界にて撮影に従事した後、写真家として独立。現在は八ヶ岳を拠点に全国の自然風景や野生動物などを撮影。雑誌新聞の寄稿、写真講師など幅広く活動。日本写真家協会・日本風景写真家協会会員。
組写真の部

四方伸季
私が嫉妬するような最強の組写真のご応募を!
組写真は、特別な一枚で勝負する単写真と違って、テーマと構成さえしっかりしていれば、秀でた一枚がなくても作品にできます。テーマに紐付いた写真を複数「繋ぐ」だけなので、組写真の作品を創ること自体は決して難しいことではなく、初心者の方にも十分楽しんでいただける写真表現です。私は組写真の基本構成は3枚組だと考えますが、今年の審査でも4枚組や5枚組で構成された応募作品で、「1 枚多い」ことが予選を突破できない原因となっています。作品のテーマやストーリーの構成をシンプルに単純化したほうが、観手の意識が散漫にならず、作品を目にした瞬間に作画意図がストレートに伝わりやすくなるということを心に留めておいてください。
しかた・のぶとし
学生時代よりコンテスト中心に作家活動を行う。プリントにこだわり、勝つための「最強の写真」を追求。月例100カ月連続入賞記録、本誌年度賞2年連続1位等の記録を保持。(公)日本写真家協会会員、エプソンプレミアム講師など。自称「紙フェチ」
歴代審査員 1974年〜2026年
| 審査年 | 中・上級コース ネイチャーフォトの部 自然の広場 (85〜90年) |
中・上級コース 自由作品の部 カラー写真の部 |
初級コース 自由の部 レッツ!スナップ (00〜06年) キャビネサイズB部 |
初級コース ネイチャーの部 レッツ!ネイチャー (00〜06年) キャビネサイズA部 ビギナーの部 |
黒白写真の部 モノクロ作品招待席 (05年〜) |
組写真の部 | カラー大型フォトサロン | サービスサイズ | レディース | 中・高校生 | ジュニア・カラー | ジュニア・白黒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 並木 隆 菊池哲男 秦 達夫 |
榎並悦子 清水哲朗 山﨑友也 |
今井しのぶ | 井上嘉代子 | 立木義浩 | 四方伸季 | ||||||
| 2025 | 三好和義 深澤武 吉住志穂 |
熊切大輔 佐藤倫子 岡嶋和幸 |
オカダキサラ | 萩原れいこ | 立木義浩 | 四方伸季 | ||||||
| 2024 | 三輪 薫 GOTO AKI 喜多規子 |
山岸 伸 鶴巻育子 山口規子 |
佐藤かな子 | 栄馬智太郎 | 立木義浩 | 小澤太一 | ||||||
| 2023 | 前川貴行 米 美知子 岡本洋子 |
林 義勝 佐藤仁重 藤村大介 |
鈴木サトル | 酒井梨恵 | 立木義浩 | 小澤太一 | ||||||
| 2022 | 前川彰一 辰野 清 古市智之 |
榎並悦子 佐藤倫子 秋元貴美子 |
鈴木知子 | 平松佑介 | 立木義浩 | 熊切大輔 | ||||||
| 2021 | 並木 隆 福田幸広 深澤 武 |
野町和嘉 山崎友也 四方伸季 |
ミゾタユキ | 喜多規子 | 立木義浩 | 熊切大輔 | ||||||
| 2020 | 相原正明 田中達也 吉住志穂 |
ハービー・山口 山口規子 渋谷敦志 |
村上悠太 | 岩橋宏倫 | 立木義浩 | 清水哲朗 | ||||||
| 2019 | 三好和義 菊池哲男 GOTO AKI |
英 伸三 元田敬三 鶴巻育子 |
藤村大介 | 石井秀俊 | 立木義浩 | 清水哲朗 | ||||||
| 2018 | 山口高志 高砂淳二 秦 達夫 |
榎並悦子 小松健一 公文健太郎 |
佐々木啓太 | 岡本洋子 | 立木義浩 | 岡島和幸 | ||||||
| 2017 | 辰野 清 鈴木一雄 古市智之 |
齋藤康一 織作峰子 HARUKI |
諏訪光二 | 深澤 武 | 立木義浩 | 岡島和幸 | ||||||
| 2016 | 丹地保尭 前川貴行 豊田直之 |
蜂須賀秀紀 井賀 孝 タカオカ邦彦 |
佐藤倫子 | 斎藤裕史 | 立木義浩 | 大西みつぐ | ||||||
| 2015 | 新井幸人 岩木 登 福田健太郎 |
熊切圭介 飯島幸永 林 義勝 |
山﨑友也 | 吉住志穂 | 立木義浩 | 染谷 學 | ||||||
| 2014 | 三輪 薫 川隅 功 竹下光士 |
山口勝廣 築地 仁 佐藤秀明 |
田邊和宜 | 並木 隆 | 立木義浩 | ハナブサ・リュウ | ||||||
| 2013 | 中村征夫 江口愼一 米 美知子 |
木村惠一 大石芳野 ハービー・山口 |
岡嶋和幸 | 秦 達夫 | 立木義浩 | 小松健一 | ||||||
| 2012 | 吉野 信 北中康文 田中達也 |
熊切圭介 管 洋志 蜂須賀秀紀 |
染谷 學 | 前川彰一 | 立木義浩 | |||||||
| 2011 | 竹内敏信 丹地保堯 山口高志 |
齋藤康一 森井禎紹 長倉洋海 |
桜井 秀 | 菊池哲男 | 立木義浩 | |||||||
| 2010 | 鈴木一雄 | 英 伸三 | 榎並悦子 | 前川貴行 | 立木義浩 | |||||||
| 2009 | 丹地敏明 | 木村惠一 | 蜂須賀秀紀 | 米 美知子 | 立木義浩 | |||||||
| 2008 | 江口愼一 | 小松健一 | 徳光ゆかり | 辰野 清 | 立木義浩 | |||||||
| 2007 | 石橋睦美 | 中谷吉隆 | 川合麻紀 | 福田健太郎 | 立木義浩 | |||||||
| 2006 | 竹内敏信 | 大西みつぐ | 神立尚紀 | 新井幸人 | 立木義浩 | |||||||
| 2005 | 吉野 信 | 栗原達男 | タカオカ邦彦 | 鈴木一雄 | 立木義浩 | |||||||
| 2004 | 栗林 慧 | 齋藤康一 | 築地 仁 | 小林義明 | 佐藤秀明 | |||||||
| 2003 | 丹地保堯 | 高橋 曻 | ハービー・山口 | 豊田芳州 | 杵島 隆 | |||||||
| 2002 | 三輪 薫 | 長友健二 | 飯島幸永 | 海野和男 | 長野重一 | |||||||
| 2001 | 横山 宏 | 野上 透 | 小松健一 | 北中康文 | 藤井秀樹 | |||||||
| 2000 | 丹地敏明 | 児島昭雄 | 徳光ゆかり | 江口愼一 | 桑原史成 | |||||||
| 1999 | 秋山庄太郎 白籏史朗 吉野 信 山本建三 |
中谷吉隆 | 川津英夫 | 田中達也 | 英 伸三 | |||||||
| 1998 | 秋山庄太郎 白籏史朗 吉野 信 山本建三 |
中谷吉隆 | 川津英夫 | 田中達也 | 英 伸三 | |||||||
| 1997 | 秋山庄太郎 白籏史朗 吉野 信 山本建三 |
熊切圭介 | 林 義勝 | 八木祥光 | 松本徳彦 | |||||||
| 1996 | 秋山庄太郎 白籏史朗 吉野 信 山本建三 |
熊切圭介 | 林 義勝 | 八木祥光 | 松本徳彦 | 村岡秀男 | ||||||
| 1995 | 秋山庄太郎 中村正也 竹内敏信 川口邦雄 |
木村惠一 | 小方 悟 | 高橋扶臣男 | 雪松 覚 蜂須賀秀紀 |
野上 透 | 桜井 始 | |||||
| 1994 | 秋山庄太郎 中村正也 竹内敏信 川口邦雄 |
木村惠一 | 小方 悟 | 高橋扶臣男 | 雪松 覚 蜂須賀秀紀 |
野上 透 | 桜井 始 | |||||
| 1993 | 秋山庄太郎 中村正也 竹内敏信 川口邦雄 |
藤井秀樹 | 大山謙一郎 | 高橋扶臣男 | 雪松 覚 蜂須賀秀紀 |
三輪 薫 | 森井禎紹 | |||||
| 1992 | 秋山庄太郎 中村正也 竹内敏信 川口邦雄 |
藤井秀樹 | 大山謙一郎 | 高橋扶臣男 | 雪松 覚 蜂須賀秀紀 |
三輪 薫 | 森井禎紹 | |||||
| 1991 | 秋山庄太郎 中村正也 竹内敏信 川口邦雄 |
大竹省二 | 蜂須賀秀紀 | 雪松 覚 蜂須賀秀紀 |
木村仲久 | 秋山庄太郎 | 雪松 覚 | 徳光ゆかり | ||||
| 1990 | 川口邦雄 | 大竹省二 | 蜂須賀秀紀 | 齋藤康一 | 木村仲久 | 秋山庄太郎 | 徳光ゆかり | |||||
| 1989 | 高田誠三 | 稲村隆正 | 三輪 薫 | 林 忠彦 | 秋山庄太郎 | 蜂須賀秀紀 | ||||||
| 1988 | 高田誠三 | 細江英公 | 児島昭雄 | 大竹省二 | 秋山庄太郎 | 蜂須賀秀紀 | ||||||
| 1987 | 高田誠三 | 細江英公 | 沼田早苗 | 大竹省二 | 秋山庄太郎 | 蜂須賀秀紀 | ||||||
| 1986 | 秋山庄太郎 | 中村正也 | 齋藤康一 | 植田正治 | 秋山庄太郎 | 蜂須賀秀紀 | ||||||
| 1985 | 秋山庄太郎 | 中村正也 | 齋藤康一 | 植田正治 | 秋山庄太郎 | 蜂須賀秀紀 | ||||||
| 1984 | 中村正也 | 蜂須賀秀紀 雪松 覚 |
植田正治 | 秋山庄太郎 | 高田誠三 | 齋藤康一 | ||||||
| 1983 | 中村正也 | 蜂須賀秀紀 雪松 覚 |
植田正治 | 秋山庄太郎 | 高田誠三 | 齋藤康一 | ||||||
| 1982 | 中村正也 | 松田二三男 中谷吉隆 |
植田正治 | 秋山庄太郎 | 齋藤康一 | |||||||
| 1981 | 三木 淳 | 松田二三男 中谷吉隆 |
植田正治 | 秋山庄太郎 | ||||||||
| 1980 | 三木 淳 | 松田二三男 中谷吉隆 |
中村正也 | 秋山庄太郎 | ||||||||
| 1979 | 三木 淳 | 中谷吉隆 | 中村正也 | 林 忠彦 | 秋山庄太郎 | |||||||
| 1978 | 中村正也 | 三木 淳 | 林 忠彦 | 秋山庄太郎 | ||||||||
| 1977 | 中村正也 | 三木 淳 | 林 忠彦 | 岩宮武二 | ||||||||
| 1976 | 秋山庄太郎 | 林 忠彦 | 岩宮武二 | 秋山青磁 | 秋山青磁 | |||||||
| 1975 | 秋山庄太郎 | 林 忠彦 | 秋山青磁 | 秋山青磁 | ||||||||
| 1974 | 秋山庄太郎 | 林 忠彦 |